Pickup
2021.02.20
インタビュー | 大嶋 光昭×西村 真里子
「世界トップクラスの発明王」が語る、知財が生み出す光とは。
パナソニック 株式会社, パナソニック ホールディングス 株式会社

手振れ補正、著作権保護技術、デジタル放送、高速モバイル通信など多分野で世界初の基本技術を開発し、1300件あまりの登録特許を取得している世界トップクラスの発明家、大嶋光昭氏。彼が開発した技術はパナソニックの経営に大きく貢献しており、特許ライセンス収入面での貢献度も大きい。現在の生活に欠かすことのできない携帯電話の通信方式技術にも、大嶋氏が30年前に開発した基本特許技術が採用されている。
このような10年から数十年先の長期的な未来を見通し、世の中を変えるイノベーションを起こし続ける大嶋氏と、世界中のコンベンションやカンファレンスを飛び回り、最先端のものづくりの現場や数多くの経営者たちと向き合ってきた西村真里子氏が、「知財が発する光と、それを生み出す方法や環境」について語り合った。
「世界的イノベーター」が生まれるまで
西村
大嶋さんは「シリアルイノベーター」つまり、革新的な技術を発明して市場に送り出すことを何度も繰り返し行う人として、この言葉の提唱者であるイリノイ大学のブルース・A・ボジャック教授の本にも紹介されています。改めてイノベーターとはどういう人だとお考えでしょうか?
大嶋
今でこそ「イノベーション」をテーマに多くの企業で講演をさせてもらっていますが、松下電器産業(現パナソニック)に入社したときは全くの凡人でした。入社後は「無線研究所(無線研)」に配属されたのですが、そこのミッションは「他ではやっていない世界初、世界最高の研究をやる」でした。いわゆる優等生タイプの技術者が集まる「中央研究所」とは異なり、無線研には一風変わった人たちが集められていて、世の中にないテーマに挑戦すれば、たとえ三振してもその姿勢を褒められるような文化がありました。
「手ブレ補正」の技術はそこで発明したのですが、実は一度カーナビ市場で失敗しました。しかし当時全く期待されていなかったセンサーに出口を見つけようと再挑戦して、量産化されていなかった手ブレ補正のセンサーとしての新しい方式を開発しました。試作機ができたときに大阪城の周りをヘリコプターで旋回して撮影するプロモーションビデオを作りました。一方の画面は揺れ、もう一方の方は全く揺れていない。一切の説明なしで効果は一目瞭然です。その映像を見て、それまで反対だった人達も含めて全員が賛成してくれました。この特許技術はまずビデオカメラに導入しましたが、デジタルカメラに導入することで、最後発だったパナソニックのデジカメをトップシェアへ押し上げることになりました。
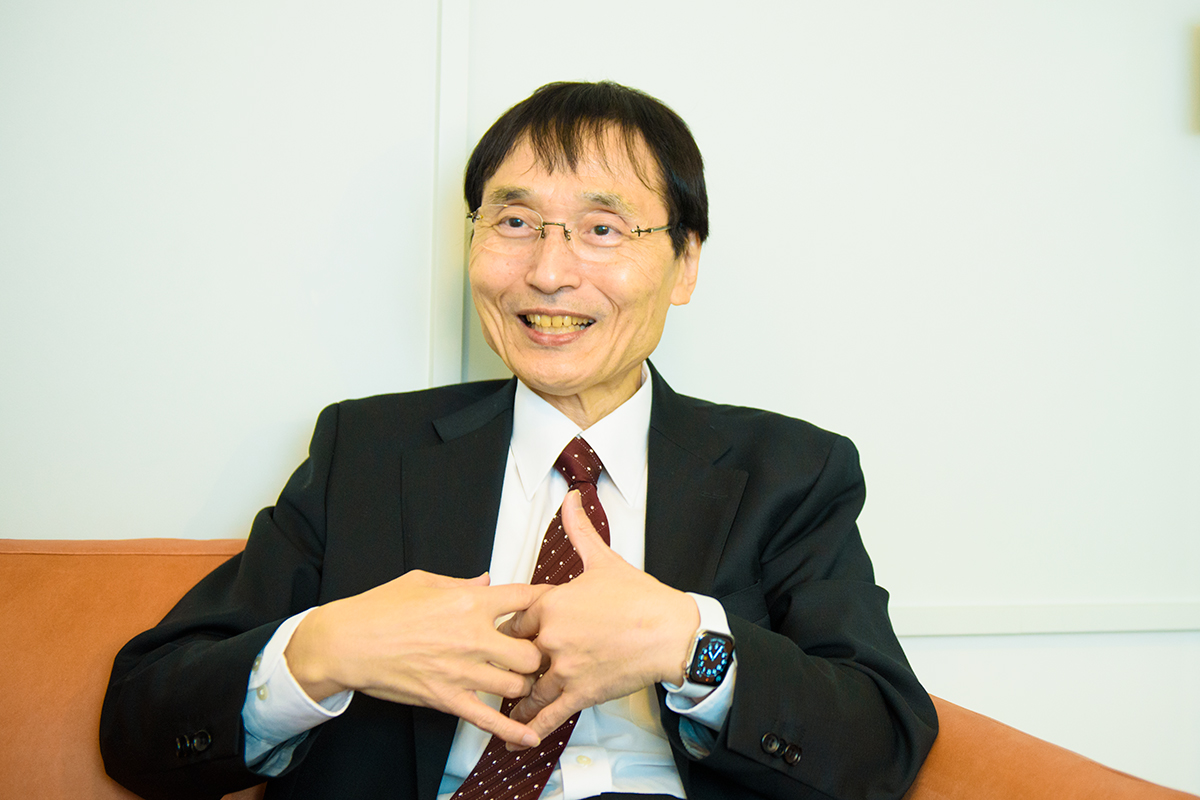
イノベーターに必要な「鈍感力」
大嶋
イノベーターと呼ばれる人はアンデルセンの寓話の「みにくいアヒルの子」みたいなもので、他の人と違ったことをやっているため周囲から批判を受けます。イノベーターには、それでも気にしない「鈍感力」が大事だと思います。私も若い頃はあまり周りの批判に気づいてなかったのですが、それはどうやら上司がかばってくれていたこともあったようでした。たまたま助けてくれる理解者に恵まれていたのですね。「みにくいアヒルの子」を白鳥に育てるためには、目利き力があるパトロン役の存在が大切だと思います。
西村
鈍感力とはタフなメンタリティのことでもありますね。周りが理解してくれない場合の立ち回りも上手くいったのでしょうね。私もIBMに在籍していた時、通常のレポートラインを越えてトップに提案するエスカレーションの仕組みを使ったことがあります。
大嶋
「直訴」ですね。ただ上申するだけではなく、ここぞと思う時には命をかけるくらいの意気込みで直訴することが大事です。フランスの哲学者・パスカルは「人間は自分に理解できない事柄は否定したがる」と言いましたが、本当に自信のあるものであれば、周りが反対したり止めたりしても、根気よく理解者をみつけることが重要です。
とはいえ私も人生で一度だけ、どん底に落ち込んだことがあります。入社5年目に研究職から事務職に異動になったのです。失って初めて研究開発の仕事の素晴らしさに気がつきました。元の仕事に戻るために終業後、夜遅くまで研究所の図書室でひたすら勉強しました。毎月1つの新しい技術分野を勉強し、その分野の特許を出願することを続けました。わからないことがあると、よく社内の専門家に聞きに行きましたが、彼らは忙しいので、ただ質問をするだけでは会ってくれません。しかし具体的なアイディアを持って提案しにいくと話を聞いてもらえました。必ず毎月1件、平均すると年19件の特許出願、それを3年続けました。これが今の「多分野型発明家」につながる私の転機でした。

オープンイノベーションの現状
西村
大嶋さんも私も「100BANCH」(*1)のメンターを担っていますが、大手企業とベンチャー企業の「オープンイノベーション」についてはどうお考えでしょうか?
大嶋
今の時代に日本で大きなイノベーションをおこすには、ベンチャーだけに任せるのではなく、成熟企業の力を上手く使うのが早いと思います。日本のスタートアップの投資規模は0.5億円からせいぜい10億円程度が多い。一方、欧米は歴史的に芸術分野で築き上げられたパトロン文化があるので投資金額の桁が違います。小規模のスタートアップなら国内でもいいと思いますが、大型のスタートアップで成功を狙うなら海外に出るのがいいのではないでしょうか。
マインドは別として、ベンチャーの技術力はまだまだ大企業の研究者にはかないません。ただ、大きな組織では「0→1(無から有を生む)」型テーマが生まれにくい。昔はイノベーションを起こさなくても利益を上げることができましたから、社内にイノベーターがいなくてもよかった。しかし今は事業に余裕がなくなってきているので、投資効率が高い「0→1」型のイノベーションとなる技術やソリューションを生み出さない限り日本企業は復活しません。累積で数千億円の事業収益を生むような大きなイノベーションへの挑戦はリスクを伴いますので、技術や人材に対する目利き力や経営者の勇気も問われます。
西村
例えばArm社が買収した「Treasure Data」のように大きくプレーしたい日本のベンチャーが長期プランを持ってシリコンバレーで挑戦したり、あるいは「NeuralX」のようにUCLAでパテント申請してからスタートアップする企業もあります。大企業のトップの意識も大分変わってきているように感じられますね。

「発明とイノベーション」の違いは「出口」
大嶋
「イノベーターが参加しないで作ったイノベーション組織」がよくありますが、殆んど機能しませんね。そこに多いのは、「アドミニストレーター(管理者)」タイプの人材がトップに立っているケース。これまでイノベーションを全く起こしたことがない人がトップに立っても、本当のイノベーションは起こせません。
発明とイノベーションの違いは「出口」があるかどうかです。アカデミックなレベルが高い人は発明はできますが、出口となる市場や事業が見えていない場合が多いと思います。イノベーターは、アカデミックなレベルとしてはトップではないかもしれませんが、出口が見えているので無駄な研究をあまりしません。出口が見えるには訓練が必要ですが、私の場合は、無線研で学びました。無線研では出口がない研究はさせてもらえなかったからです。独立予算だったこともあり、研究費を確保するためにどういうシーンで自分の研究が役立つかを日々考えるように追い込むんですね。出口は単なるタイミングの問題です。どんな技術でもいつか必ず出口のタイミングが来るとなれば、自らそのタイミングを考えるようになります。それは無線研を作った松下幸之助(パナソニック創業者)の狙いでもあったのでしょうね。
私は挑戦を続ける内に、段々と出口のタイミングを読むのが得意になっていきました。短期的成果を狙う場合は役に立ちませんが、あらゆる分野の技術史の周期を追っていくと長期的なトレンドが見えてきます。技術の進歩には長期的な大きな波と短期的な小さな波があり、自分の現在の技術が成長期なのか成熟期に入っているのか、これから先に必要となる技術なのかがわかるようになります。
(*1)「100BANCH」:パナソニック、ロフトワーク、カフェ・カンパニーが「100年先の世界を豊かにするための実験区」として渋谷に開設した複合施設。35歳未満の若者リーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラムにて、大嶋や西村ら各分野のトップランナーがメンターを務める。
これからは機能と感性のハイブリッド
西村
これからものづくりや研究の世界に飛び込もうとする若い人たちが大事にすべき視点などはありますでしょうか?
大嶋
私たち先輩技術者がこれまで追求してきた「機能価値」とは別に「感性価値」が重要になってきましたが、これは若い人が得意とするものでしょう。今、勢いのあるGAFAなどの企業はどちらかといえば感性価値を武器にして大きくなってきたといえます。
西村
日本でも「大企業の技術力」と「スタートアップならではの感性」を繋ぐことで、面白いイノベーションが起こせるのではないかと言われていますね。
大嶋
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われた1980年代は、世界でアンチパテント(*2)と呼ばれるトレンドがあり、モノづくりの上手い日本が大きく成長を遂げました。つまり「1→10(開発、設計)」や「10→100(量産化、事業化)」をひたすらやって勝ってきたのです。そのときに活躍した技術人材を「0→1」にシフトできればよかったのですが、そこが難しかった。
1990年代になると世界のトレンドがアンチパテントからプロパテント(*3)へ移行し、日本が得意な「モノ(有形価値)」から不得意な「コト(無形価値)」へシフトして、日本企業にもイノベーションが求められました。イノベーションには多様性が重要となりますが、日本は文化的にも地政学的にも同質性が強かったため、早くから多様性を受け入れてきた欧米と大きな差がついてしまった。このこともあり、大きなイノベーションがおこらないまま、後に「失われた20年」と呼ばれる長い停滞期に入ることになったのです。
西村
多様性を大切にすることと同時に、「違和感」を持つことも重要なように思います。周りが当たり前にしている中で何かひっかかるものがある。そうした自分の内にある経験や感覚を元にスタートアップする人も多いです。
違和感を大切に、「リンク力」を磨く
大嶋
日本は同質性の強い社会であるが故に、小さな違和感つまり兆候を見過ごしがちですが、それを「なんでだろう?」という視点でとらえると課題に気がつくことができます。そうやって自分の内在的テーマを追求する人が実は一番強い。自分の経験から生まれたものはブレませんから。
そこで大事なことは、この観察力に加え、一見関係ないもの同士を結びつける「リンク力」です。例えば、私は日々観察し、観察で得たことをリンクさせて思いついたことを手帳にメモしています。先入観にとらわれず、どうしたら世の中をよくできるのか、どういう技術を使えばもっと便利になるのか、常に考えて過ごしてきました。観察力というのは先ほどの感性力と関連しますが、科学者でも文系の会社員でも大事です。
新しい技術や事業の開発だけでなく、既存の技術や事業を組み合わせていく場合でも、小さな兆候をとらえて人と違う発想をどれだけできるかが重要。それには好奇心が大事で、歳を取ってもいかにこの好奇心を持続させられるかが鍵です。

西村
今は大嶋さんが若手の育成において「みにくいアヒルの子」を守る「お母さんアヒル」のような存在になっていますね(笑)
大嶋
私のいた無線研は自由に新しい研究ができましたが、技術者を見る目は厳しかったと思います。ホームランを狙うことは大事ですが、三振を恐れずに挑戦を続けること。そうして成功を積み重ねることで「与信額」を上げていくことも必要です。私の場合、若い頃に数百万円の小規模な予算で研究開発を始めましたが、実績を重ねることにより「与信額」が上がり、十数年後には数億円の大規模な予算による研究開発も任されるようになりました。それは成功した実績があるからできたことです。
大企業の中では新しいことに対する抵抗が大きいため、社内に応援してくれるパトロンを見つけることが大事です。同時に上に立つ人は、いかに目利き力を発揮して若い人のチャレンジを見守れるかが重要です。「0→1」の世界は材料開発に似ていて分岐点が多いため、詳細な年間計画が立ちません。それは決して計画書を作る能力がないということではないんですね。成功体験を重ねた技術者は目利きができるようになるので、次のステップへの分岐点で方向を間違えずに進めます。イノベーターを目指す若手なら、分岐点での進路変更の際に「1」を聞いたら「10」を理解してほしいと思いますが、なかなかついて来てくれません。説明するのは大変なので少なくとも「3」くらいで「10」をわかってほしいんですけれどね(笑)。
いずれにしても、将来ジャンボジェットの機長を目指している人が、セスナ機の練習しかしなければいつまで経ってもジャンボ機には乗れませんよね。最終的にどこをゴールとして日々を過ごすか。そうした「大志」を持っているかどうかは重要ですね。最近はスモールビジネスのスタートアップを志す若い人が多いように思いますが、ジャンボ機を操縦できるような高いポテンシャルを持った人であれば、大きく育てていかないともったいないと思います。
(*2)アンチパテント:独占行為を規制することにより自由な競争と技術の普及を図り、ひいては産業の発達を図るとする政策や考え方。
(*3)プロパテント:アンチパテントとは反対に、特許法による知的財産の保護と独占を重視する政策や考え方。








