Pickup
大阪・関西万博
2025.08.21
インタビュー | 石黒 浩×内田 まほろ×遠藤 治郎
記憶に残る万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」の舞台裏、異才が集うチームによる空間設計

大阪・関西万博の中でも、大きな反響を呼んでいるのが万博シグネチャーパビリオンの「いのちの未来」だ。プロデューサーはロボット工学の第一人者・石黒浩氏で、「いのちを拡げる」というテーマのもと、アンドロイドやロボット、CGアバターなど先端技術を駆使した没入型の展示体験を通じて、来場者一人ひとりが未来を考える場となっている。
今回はプロデューサーを務めた石黒 浩氏のほか、企画統括ディレクターの内田 まほろ氏、建築・展示空間ディレクターの遠藤 治郎氏と、知財図鑑代表 出村光世との対談を通して、本プロジェクトの舞台裏や伝えたかったメッセージを紐解いていく。

▼知財図鑑のYouTubeチャンネルでも、対談の様子を動画で公開しています。
座談会動画 はこちら(YouTube)

シグネチャーパビリオン「いのちの未来」/Photo by 知財図鑑
「いのちの未来」が示す万博の新しい展示のあり方
出村
万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」は、SNSなどでも多くの情報が出ていますが、それとは別に自分の言葉で感想を語れるくらい体験が記憶されているというか、今でも全体の内容を鮮明に思い出せるほどの強烈な体験でした。本当に感銘を受けましたし、心から素晴らしいと感じました。
そんななか、まずはロボット工学の第一人者である石黒先生に、今回のプロジェクト全体に込めた想いやビジョンを、あらためてお聞かせいただければと思っています。
石黒
僕が伝えたいことのほとんどは著書『いのちの未来 2075 人間はロボットになり、ロボットは人間になる』に書いてありますが、そちらもぜひ参考にしていただければと思います。
アンドロイドのソフトウェアにおいてはATRのチームがプログラムをよりシンプルに扱いやすくするために何度も改良を繰り返しました。また、来場者の位置をセンサーで正確に検知し、その人と目を合わせる動きができているのも大きなポイントです。
さらに、メインの展示ではありませんが、最も技術的にすごいのは展示の出口にいる「Yui」というアンドロイドで12時間稼働が可能です。これはムーンショットプロジェクトが関わっていることもあって、多くの先端技術が取り入れられており、今後実用化に最も近いロボットになっています。
石黒
僕自身、今回のプロジェクトではロボット工学の第一人者というよりもパビリオンのプロデューサーとしての役割に重きを置いてきました。従来の万博やパビリオンというのは、「新しいテクノロジーを見てみんなが驚く場所」というイメージが強かったと思います。
でもテクノロジーがこれだけ進んだ時代だからこそ、来場者一人ひとりが「これからの未来をどう生きるか」を考えていくパビリオンであるべきだと考えていました。そのことをプロデューサーに就任した時から一貫して主張してきましたが、万博の関係者の皆さんが私の思いをしっかりと受け止めてくれて、最終的には子どもから大人まで誰もが未来について考えられる素晴らしい展示にまとめてくれたと感じています。
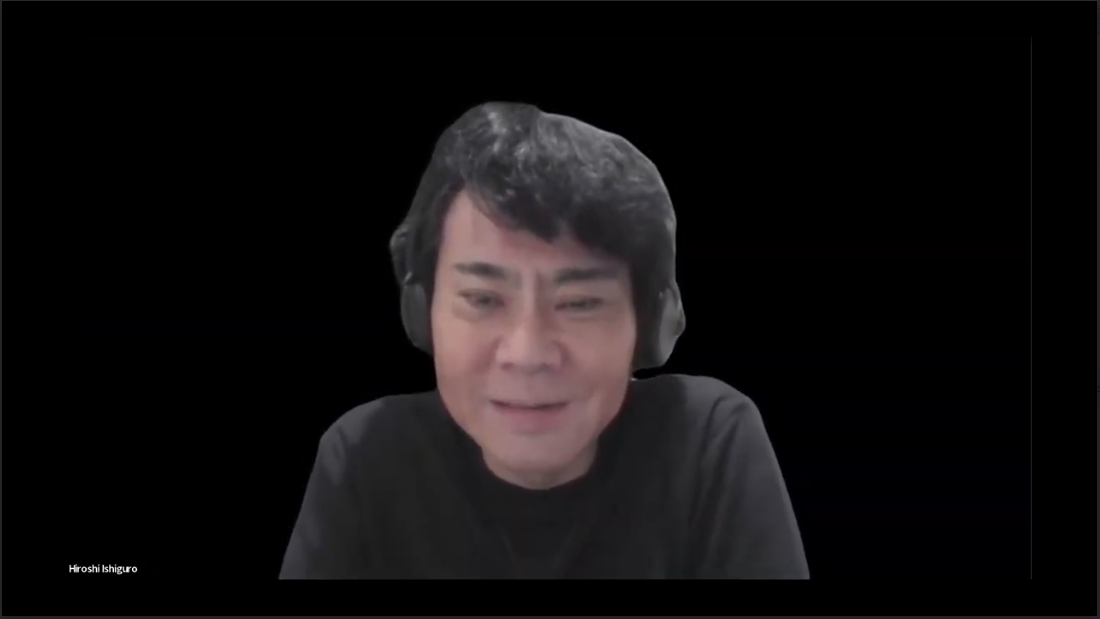
出村
これまで、開業に向けては強い信念を持って取り組まれてきたと伺っています。実際に多くの方々が来館されるようになって、さまざまな意見があると思いますが、来場者の反応にはどのような傾向があると感じていますか?

石黒
会場には3つのゾーンがあって、導入パートのゾーン1「いのちの歩み」では日本人が「モノ」にいのちを宿してきた歴史を展示しています。ゾーン2「50年後の未来」では来場者自身に50年後の未来社会を深く考えてもらう構成になっています。特にゾーン2では、非常に優れたシナリオライターの方々が関わっていただいたこともあり、そのストーリーに多くの方が「心を動かされている」のが印象的でした。「感動して涙を流した」という声も数多く届いていて、たくさんの人がその物語に深く入り込みながら、自分の未来について真剣に向き合ってくれていると感じています。
そして最後のゾーン3「1000年後のいのち“まほろば”」では、非常にリアルで美しいアンドロイドが登場するのですが、人によって「すごく綺麗だった」と感じる人もいれば、「ちょっと怖かった」と受け取る人もいて、反応はさまざまです。ただ共通して言えるのは、「これまでに見たことのないものを体験した」という驚きやインパクトを、多くの来場者が口にしている点だと思います。

出村
内田さんにも同じような質問をしたいのですが、実際に万博が始まってみて、想定していた意図とは少し違う受け取られ方をしている感じたようなことがあれば、ぜひお聞かせいただけますか?
内田
私は設計者として、こうあるべきだという明確な意図を持ってパビリオンを制作しました。なので、予想外の反応というのはあまりなかったんです。むしろ、完成度も含めて設計した通りに来場者の皆様に意図が伝わっているかという点がずっと気になっていました。それは、完成に近づくにつれて作品への愛着もどんどん強くなっていきますし、私たち自身が一番その展示のことを理解している存在でもあるからこそなんですよ。

内田
私たちが最も展示を理解しているからこそ、「初めて見る人にどこまで伝わるか」という不安もありました。120%の想いを込めても100%しか伝わらない、というのはものづくりではよくあることですが、蓋を開けてみると、今回の展示では100%で作ったものが120%になって伝わっているという、予想以上の反響に驚いています。正直、「これは難しいな」と思って帰る人が半分以上いるかもしれないと予測していた部分もあったんです。
でも、実際には多くの方々が感動して帰ってくれました。ゾーン2の感動的なストーリーは理解されやすいと思っていましたが、ゾーン1の導入やゾーン3の飛躍した世界観や突き抜けた未来への繋がりまで、思った以上にきちんと理解してもらえていることに意外性を感じていますね。
これもひとえに、今回のチームの強さのおかげだと思っています。

鑑賞後も語りたくなる“読後感”─来場者が持ち帰る「いのちの未来」
出村
僕自身、これまでいろんなSF作品を読んだり観たりしてきましたが、「きっと未来はこうなっていく」と腑に落ちる感覚が、今回はすごく早かったんですよ。特に最後のシーンでは鳥肌が立ったというか。観た後もモヤモヤがずっと残っていて、何かが心の奥に残っているような“気持ちのいい消化不良”みたいな感覚が印象的でした。
内田
まさに“読後感”みたいなものですよね。本当に予想外だったのは、鑑賞後に交わされる議論の多さでした。正直に言うと、「面白かったね」とか「良かったね」くらいで終わると思っていたんですが、色々な方が「帰り道にずっと『いのちの未来』の展示について語り合っていた」とか、「家に帰ってからも、ずっと展示のことを話していた」という感想を聞きました。
ある意味、トラウマになるほどの心に残る体験ができたというのは、あまり想像していませんでした。おそらく、現代の人々が感じている自分自身の存在と未来のテクノロジーとの関係性に対する高い感度と、うまく言葉にできない消化不良の違和感みたいなものが、見事に合致した結果ではないかと感じています。
出村
プロジェクトを推進していく際に、内田さんと石黒先生との間では実際にどんなやり取りをされてきたのでしょうか?
内田
石黒先生は発想があちこち飛ぶというよりも、ものすごく理論的で筋が通っている方なんですよ。もちろん、展示表現の仕方や一般の方々の受け止め方、動線やデザインの細かい部分については、私たちの方が専門知識を持っていますので、「そこはちょっと違うと思います」とはっきり言うこともあります。でも、それは相手の立ち位置や役割分担、専門性を尊重したうえでのやり取りであって、基本的には率直な意見交換を行いながら、プロジェクトを前に進めてきました。
加えて、今回参加してくれた演出・デザイン・運営に至るプロフェッショナルなチームは本当にすごいなと感じています。運営面はあまり注目されにくいですが、今回の展示がスムーズに体験できるのも、裏で運営が支えてくれているからであり、感動体験の質を高める上でも欠かせない要素なんです。運営チームが来場者をちょうどいいタイミングで入れていき、各所の細かいディテールの積み重ねがあって、初めて成り立っている展示空間だとあらためて思いますね。

遠藤
本当にみんなが同じゴールをしっかり共有できていたからこそ、毎回の打ち合わせでも自然と意見がまとまり、お互いに納得しながらスムーズに物事が進んでいきましたね。
内田
今回は各業界の部長クラスの方たちが現場で動いてくれていて、トラブルが起きたときの対処の仕方や各方面との交渉、コミュニケーション面など、かなり経験豊富な大人のチームだったと思います。若いメンバーも参加してくれていましたが、そのバランスもすごく良かったなと感じています。
出村
素晴らしいですね。まさにパートナーシップで成り立っているチームだったというのが理解できました。
石黒
実を言うと、当初は万博パビリオンのプロデューサーをやるかどうか、半年間ほど考えたんです。そこが根本的にあったなかで、チームのみんなが「万博をやることの意義」を僕の意見も踏まえながらしっかりと考えてくれたのは大きいと思っています。
内田
だからこそ納得感があって、「やるんだったら、もうここまでやらないとやる意味がない」というマインドをチーム全員が持っているんですよ。
不安を払拭した「降臨」の瞬間。最後の1ヶ月で見えてきた境地とは
出村
そういった意味では、与えられた仕事をこなすという感じでは全くなくて、むしろ最初はマイナスからのスタートだったのではと感じています。こうした状況から、チームの心のスイッチが切り替わったのは何がきっかけになったのでしょうか?
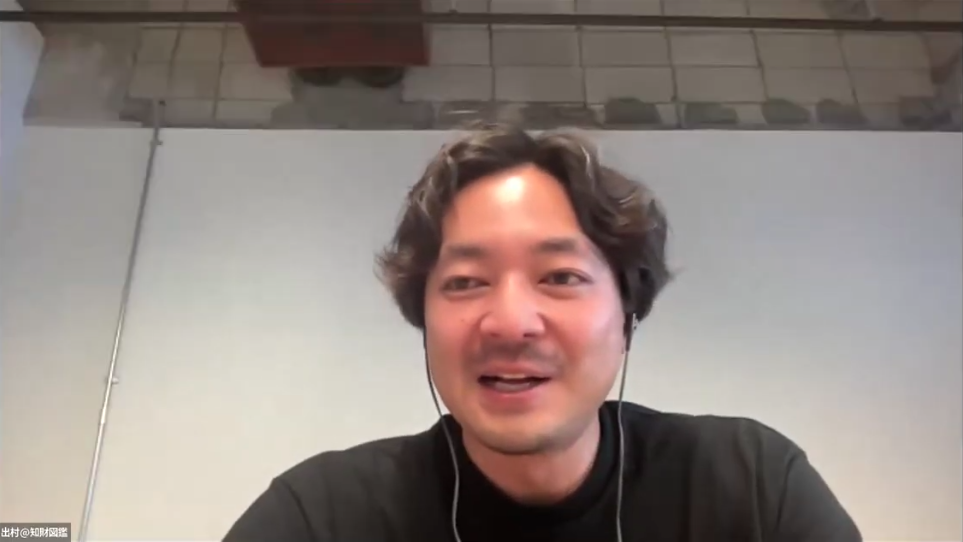
石黒
僕にとって、大きな転換点は特になかったですね。最初の半年間じっくり考えたなかで、もし万博をやるとしたら、それは新しい技術をただ見せる場ではなく「未来を考える万博にするべき」という結論に至って、自分の中でしっかり腹落ちしたからこそプロデューサーを引き受けたんです。そこから、内田さんや遠藤さんにもお声がけしたわけですが、最初からずっと同じ方向を見てやってきています。言ってることも全く変わってなくて、プレゼン資料も4年間ずっと同じスライドを使ってるくらいなんですよ。
内田
私自身も引き受けたのは、石黒先生が手掛けるなら、きっと素晴らしいものができるだろうという確信があったからです。この業界で一番先生のビジョンを理解していて、先生の面白い発想を形にできるのは自分だという自負があったので、「これはやるしかない」と思って決断しました。
遠藤
万博には、いろんな意味で課題があって、良い部分と悪い部分が複雑に絡み合ってるんですよね。例えば会場の場所の問題から政治的な要素まで、本当にさまざまなレイヤーで課題があるんですが、日本の万博は昔から“特有の座組み”があって、そこに課題があると思っているんです。
何が問題かというと、建物・運営・展示といった要素がそれぞれ別々に切り離されてしまう構造になっていること。いわば分離発注的な仕組みになっていて、本来一体となって動くべきものが別々に進んでしまうんですよ。だから、そこをどう繋ぐかが非常に肝になったわけですね。
今回のプロジェクトでは、従来の万博の常識を打ち破り、分断をなくしたいという話を内田さんから最初に聞いていました。石黒先生のビジョンを実現するために、建築から展示、物語構成に至るまで、すべてを連続性のある流れとしてつなげたいという想いが最初に共有されたからこそ、自分に声をかけてくれたんだと感じました。
でも正直なところ、プロジェクトのスケールが大きすぎて、本当に最後までうまくまとまるのかという不安は常にありました。個々のパートのクオリティは高められているものの、それがうまく融合するかは最後まで見えなかったんです。しかし、万博開幕の1ヶ月前に各パートが一気に融合し、作品として結晶化した感覚がありました。その瞬間はとても感動的で、4年半かけた意味が本当にあったと思えるものでした。そして、その一体感が来館された方にも確実に伝わっていると感じる非常に稀有なプロジェクトだったなと思いますね。

出村
万博開幕の1ヶ月前のタイミングになって、不安が一気に晴れたというのはどういう感覚だったんでしょうか?
遠藤
言葉にしづらいんですけど、何かが降りてくるような“降臨”のようなタイミングが、まさに3月に訪れたんですよ。きっと来るとは信じていましたけど、ずっと待ち続けていたものがようやく訪れた感覚でしたね。
運営と一括りに言っても、来場者にとっては現場にいるスタッフの方が全てなんですよね。お客様が視覚以外で受け取る情報や体験の質を左右するのは、まさに運営スタッフの振る舞いなんです。なので、そこがスムーズに機能しないと、全てが台無しになってしまうわけで、その点がしっかり噛み合いはじめたのが、本当に3月に入ってからだったんですよ。それぞれの分野のプロフェッショナルたちが、自分の持ち場で、ずっと全力で「もっと良くしよう」と取り組み続けてきた結果、遂に成果として形になった瞬間だったと思います。
内田
テストランや関係者の内覧の段階でも都度いろんな気づきがあって、それに応じて少しずつアップデートしてきましたし、実際にお客様入ってからも調整を重ねてきました。今がようやく、一番完成度が高い状態に近づいてきたのかなという感じですね。グッズや関連書籍なども含めて、すべてがエスクペリエンスの一部なので、それらもようやく揃ってきたという所感です。今はバーチャル面ももう少し手を加えていこうと進めているところです。
遠藤
展示体験としては1回あたり20人くらいが理想的なんです。そのくらいの人数だと、内容もしっかり伝わるし、参加者同士の一体感も生まれやすいんですよね。その一方で、多くの方に見ていただきたいというニーズもあって、現在は最大で30人を超えるくらいまで調整して受け入れている状況です。
ロボットがたくさん登場するパフォーミングアーツの可能性を見出せた
出村
万博がまだ開催中で、感動がずっと渦巻き続けているなか、皆さんがこの体験を一緒に作り上げたことで、何か新しいアイデアや次に繋がる動きはありましたか?
内田
私はチームのみんなと一緒に、今回の展示を再演できる方法を模索しているところです。今回の展示では複数のロボットが登場して、しかもお客様とものすごく近い距離で体験できる場を実現できたのは、本当に大きな意味があったと感じています。やはり、ロボットは真近で見て初めて、その動きや存在の面白さが伝わるものだと思うんですよ。今回のような展示が成立したことは、これからの展示やエンターテインメント、コミュニケーションのあり方を考えるうえで、固定概念を取っ払うことができたと思っています。
今後は、ロボットがたくさん登場するパフォーミングアーツの可能性もあるでしょうし、私たちのようにミュージアム運営に関わっている立場からすると、施設の中にもっと自然な形でロボットが存在する未来も少しずつ現実になっていく予感がしていますね。

遠藤
今回の展示構成は、本当に斬新で多層的だったと思います。まずゾーン1では、「対象物に対峙する」という基本の博物館としての基本スタイルがあって、ゾーン2ではそこから一転して、ストーリーに沿って伴走するような体験に変わっていきます。最後のゾーン3ではプラネタリウム的な360度のシアター体験が登場します。この3つのゾーンは、それぞれ全く異なる手法や構造を持ちながらも、緩やかにグラデーション的につながりつつ、ときに対比される設計はとても新鮮で、個人的にも強く印象に残りました。
そうした要素が1本の流れとして体験できる形でまとめ上げたというのは、非常に学びが大きかったですし、今後どんなプロジェクトが来ても応用できるんじゃないかと感じています。
他方で、ゾーン3の手すりとアンドロイドの距離については、何度も図面を描き直し、安全性と近さのバランスを追求しました。強制安全装置で確実に停止できるかなどの検証を繰り返しながら、いかに安全を確保しつつ、最大限に近づけるかという最適な着地点を見つけるのに非常に時間を要しましたね。そうした試行錯誤の末、内田さんの仰るような「ロボットを真近で見る体験」を作れたのはとても達成感を得ることができました。

石黒
最後の「1000年後のいのち“まほろば”」のパートは今の形もすごくいい着地にはなっているんですけど、全く新しい形に作り変えてみても面白いんじゃないかというのは話しているんですよ。もう一度ゼロから取り組んだら、もっと面白くなる可能性もあって。だから、クリエイターの誰かがある日ふと夜中にひっそり新しいバージョンを作ってくれたりしないかなと期待してたりもするんです......。
ただ、今回の展示は非常に完成度が高く、現時点でひとつの到達点としてコンプリートできていると感じています。でも、もし次にまた機会があって新たな展示を作るとしたら非常にワクワクしますね。今回の経験を通して、大きな壁を一つ越えられた感覚がありますし、「アンドロイドの展示でもここまでできるんだ」という手応えを得られたのが大きな収穫でした。
日本人だけじゃなくて、海外から来た外国人の方々も同じように、みんなが「感動して泣いた」と言ってくれるんですよ。特に意識して「外国人向け」に何か調整したわけではないんですが、万博という場で今回の展示を行った結果、誰が見ても心が動くものになっていたのはとても良かったなと思っています。
「神様のように見える存在」を感じる空間設計
出村
遠藤さんのお話を聞いていて思ったのが、私も万博で別のコンテンツづくりをしているなかで、安全基準に関しては保守的でかっちり決められてることが多いんですよね。他方で、この展示は思い切った設計だったというのが最初の印象です。ある種、触れるのをためらう緊張感みたいなものを自然と感じたというか。そんな“神聖さ”にも近い雰囲気を感じました。
内田
それはまさに狙い通りで、「神聖な存在として見せたい」というのは、先生が最初からずっと思い描いていたことだったんですよ。もちろん、そのことは言葉で説明しているわけじゃないんだけど、チームの中で「どうやって具現化するか」というのを徹底的に突き詰めてくれたんです。
最後の詰めの部分は、空間演出を手がけた金子 繁孝さんの力が本当に大きくて。衣装やデザイン、動きも大切ですが、最終的には音楽の使い方や空間の演出といった要素が重なって、“神様のように見える存在”として成立したんだと思います。
遠藤
途中で気づいたのは、「目に光が入らないと、視線が合ったようには感じられない」ということでした。最初はずっと垂直の光だけで演出し、その他の光は動かさないというルールでしたが、それを「手に光を当ててみる」ことにしたところ、手がリフレクターの役割を果たして反射光が目に届くことで「目が合う」という感覚が生まれたんです。こうした細かいブレークスルーがいくつも積み重なって、最終的に“垂直の神殿”とも言える空間になっていったんです。

内田
私は「展示」というメディアを中心に活動していて、以前から「ナラティブ」や「問いを持ち帰る」というのを展示の軸として大事にしてきました。今回もその考え方は一貫していて、それは先生とも共通認識がありましたし、チームのみんなとも通底する価値観を持っていた気がします。最初は抵抗があった人でも、時間とともに変化していったのがすごく印象的で各メンバーにとって新しい挑戦になったプロジェクトだったと思います。
石黒
もしそれぞれの分野における超専門家がチームに集結してしまっていたら、当たり前のものにしかならなかったでしょうね。
遠藤
有名な人が集まりすぎると、みんな自分のエゴのぶつかり合いになってしまいがちで、今回のような展示体験にはならなかったかもしれません。
内田
今回のプロジェクトでは、石黒先生と深く対話できる「知性」と「共感力」を重視してメンバーを選定しました。もちろん、自分のエゴを持っていること自体は歓迎していたんですが、単なる技術的な興味ではなく、先生の世界観を真摯に理解し、共に形にしようとする姿勢が不可欠だと考えていたのです。各分野のプロフェッショナルたちは、先生の構想に対して積極的に意見を交わし、それぞれの専門的な視点をもとにしっかりと提案してくれたことで、最終的に展示の質を高める原動力となりました。
出村
技術的な側面だけでなく、石黒先生の世界観を「知性」で解釈し、「共感力」で共に歩む。そのチームの在り方が、これほどのクオリティを生み出したのですね。皆さんの、先生の構想を「共に形にする」という真摯な姿勢が、この素晴らしいプロジェクトを成功へと導いた原動力だったということがよく分かりました。本日は貴重なお話をありがとうございました。
一同
ありがとうございました。
▼知財図鑑のYouTubeチャンネルでも、対談の様子を動画で公開しています。
取材:出村光世 / 編集:古田島大介、福島由香








