Pickup
2025.11.12
レポート | World Hunt
サーキュラーエコノミーの未来をかたちにする —— Hydroが描く新しい素材の風景 【World Innovators】

世界を変える素材は、思いのほか身近にある。ノルウェーのアルミニウムメーカー Norsk Hydro(以下、Hydro)は、売上高3兆円を超える世界有数のアルミニウム企業であり、素材業界の常識を覆す存在だ。単なるリサイクルではなく、「環境」「透明性」「デザイン」を軸に、アルミニウムの可能性を再定義している。
メディア「知財図鑑」を運営するKonelは、2025年のミラノデザインウィークにて、光・音・温度・触感といった五感にアプローチする「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」でFuorisalone Award 2025 テクノロジー部門のショートリストに選出された。その活動を通して目の当たりにしたのは、世界中でテクノロジーやサステナビリティに本気で取り組み、未来を変えようとするイノベーターたちの姿だった。

彼らの思想や挑戦から学び、共に次の社会を創っていく ― そんな想いから生まれたのが、「World Innovators」欧州版インタビューシリーズである。このシリーズでは、世界各地で社会課題の解決に挑む人々へのインタビューを通して、より良い未来の在り方を探る。
その第一回となる今回は、地産地消のものづくりに本気で取り組むノルウェーのアルミニウムメーカー、Hydroに注目。Hydro Extrusions コミュニケーションディレクターの Jacob Nielsen 氏 に、同社が2025年春の Milan Design Week で発表した画期的な再生アルミプロジェクト 「Hydro CIRCAL 100R」 について話を伺った。テーマは、デザインを通じた共創のあり方。再生素材が持つ新たな可能性、そして世界に広がるサプライチェーンの変革の裏側に迫る。

「素材をつくる会社」から、「未来をデザインする会社」へ
菊池:本日はお時間いただきありがとうございます。欧州ではよく知られているHydroですが、日本ではまだ名前を耳にする機会が少ないかと思います。まずは会社の成り立ちと、今のビジョンを教えていただけますか?
Jacob:Hydroは120年前、ノルウェーで水力発電からスタートしました。以来、エネルギーとアルミニウムを軸に事業を展開しています。本社のオスロを中心に、現在は世界42か国に拠点を持ち、約32,000人が働いています。上流ではノルウェーおよびブラジル、カタール、カナダ、オーストラリアの関連会社を通じて一次アルミニウムを生産しています。また、ブラジルではアルミニウムの原料であるボーキサイトを採掘し、それをアルミナへと精製しています。
下流では、押出成形事業をヨーロッパと北米で大規模に展開しており、南米や中国にも事業拠点を構えています。持続可能性は当社の存在目的の一部であり、さまざまな面で改善に取り組んでいます。その一つがアルミニウムのリサイクルで、これは環境的にも経済的にも有益です。生産工程に再び組み込むことができる地元のアルミスクラップへのアクセスが重要です。

菊池:グローバル企業でありながら、地域性を重視するのは興味深いですね。競争力の源泉はどこにあるのでしょう?
Jacob:今、顧客が求めているのは「軽い素材」ではなく「低炭素でトレーサブル(追跡可能)」な素材です。私たちのアルミニウムは、可能な限り“その土地で生産し、その土地に届ける”というサーキュラーエコノミーの思想に基づいています。たとえば北米市場向けの素材は北米で調達し、現地企業へ供給しています。当社は完全な透明性の原則を掲げており、原産地やリサイクル経路を含むすべての製品データを開示して、トレーサビリティ”を徹底しています。自動車産業のようにサプライチェーンが複雑な業界では、これは大きな信頼につながります。

持続可能性が“コスト”から“価値”へ— Hydro CIRCAL R100
菊池:とても興味深いお話です。Hydro社はこれまでもMilan Design Week(MDW)に何度も出展されていますよね。サーキュラーエコノミーの思想をデザインの場でどのように伝えていくのか、非常に印象的でした。
ところで、2025年の展示「Hydro R100」ではどのような狙いやメッセージを込められたのでしょうか?

Jacob:Hydro CIRCAL100Rは、100%ポストコンシューマースクラップ、つまり一度使われたアルミを再利用してつくられた再生アルミです。素材の純度が非常に高く、構造強度・耐久性・美観のいずれも新品のアルミと同等、あるいはそれ以上の性能を持っています。最大の特徴は、圧倒的にカーボンフットプリント(CO2排出量)が低いことです。新しいアルミを生産する際のCO₂排出量と比べ、リサイクルの場合は必要なエネルギーがわずか5%。欧州の平均排出量が 6.9 kg CO₂/kg であるのに対し、Hydro CIRCAL 100Rは 0.5 kg CO₂/kg 以下にまで削減されています。これは、世界平均であるアルミニウム1キログラムあたり14.8kg CO₂/kg よりも大幅に低い値です。


菊池:環境負荷の差が非常に大きいですね。
Jacob:世界的に、サプライチェーン全体のCO₂削減が重要視されています。特に自動車メーカーは1台あたり1000以上の部品があり、全ての供給源とCO₂排出を明確にする必要があります。Hydroの素材は「軽い」だけではなく「トレーサブルで低炭素な素材」として価値を見出されているのです。
菊池:一方で、リサイクルアルミの方が高価になるという話もありますね。
Jacob:その通りです。リサイクル材は供給量が限られており、高品質なスクラップを確保するのも簡単ではありません。そのため価格は新しいアルミよりも高くなる傾向にあります。それでも、多くの顧客はその持続可能性自体に価値を感じています。たとえば建築の外装材では「いま使っているアルミを20年後に再び使う」構想も進んでいます。素材を“使い捨て”ではなく“資産”としてとらえる考え方が、確実に広がっているのです。
菊池:環境への配慮がCSR(企業の社会的責任)ではなく、ビジネスそのものになっているのですね。
Jacob:まさに。私たちにとって環境配慮は「オプション」ではなく「戦略」です。Hydro CIRCAL 100Rは、その象徴的なプロジェクトです。
デザインの力で素材を“見える化”する —— Shapes by Hydro & Design Week
菊池:Hydroには「Shapes by Hydro」というプラットフォームがありますね。デザイナーや建築家がアルミニウム素材の可能性を探求し、創造的な活用事例を共有するためにHydroが立ち上げたプラットフォームで、オンラインと印刷メディアの両面で展開されています。素材を通じて世界中のクリエイターをつなぎ、共創の場を生み出していると伺いましたが、どのような狙いで立ち上げられたのですか?
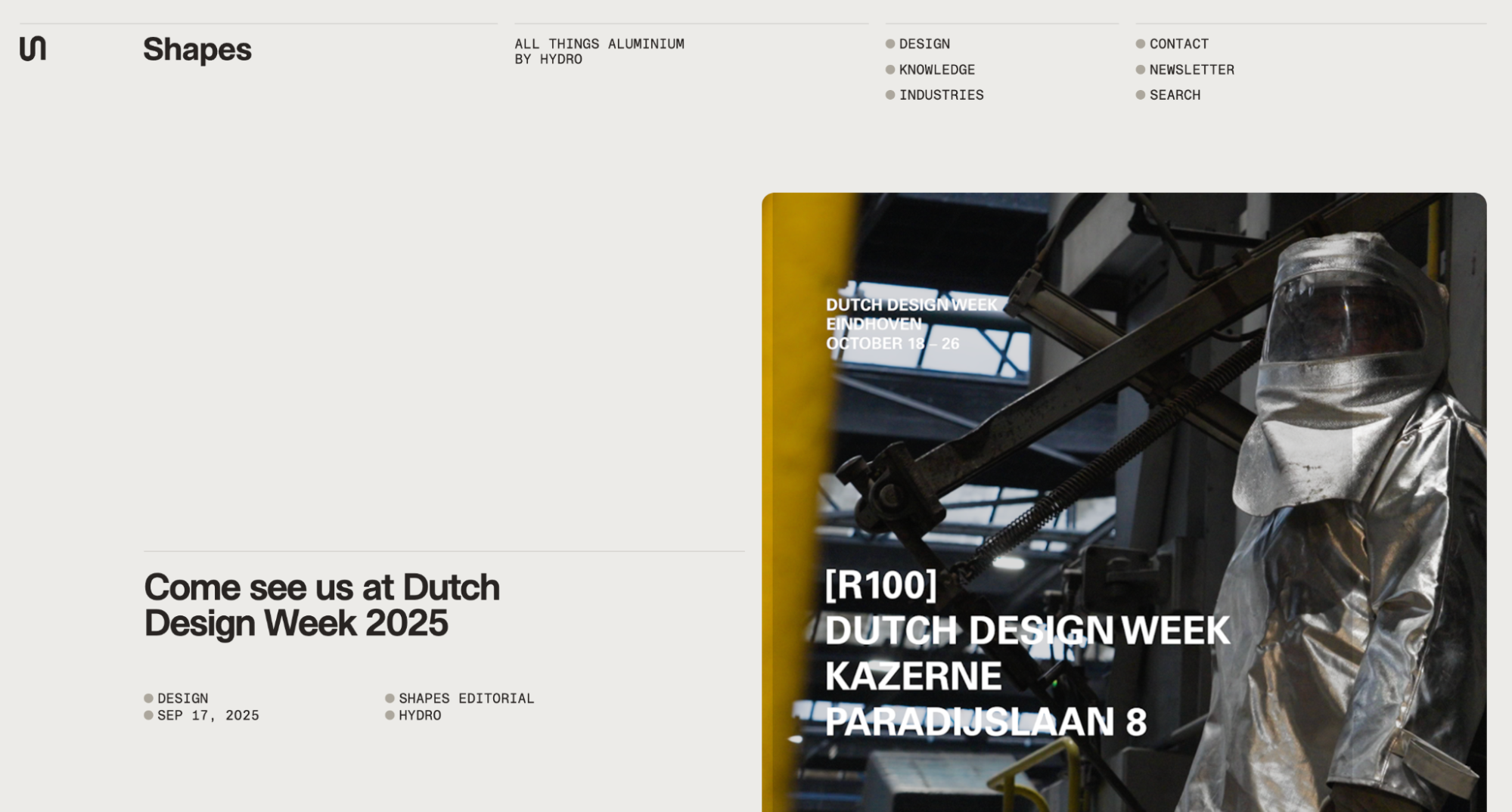
Jacob:アルミニウムは、鉄や木材と比べて歴史が浅い素材です。だからこそ、デザイナーや建築家の創造力次第で、まだまだ大きな可能性があると考えています。「Shapes by Hydro」は、素材の表情や加工の可能性を広く伝え、デザイナーやエンジニアと対話しながら素材の未来を共創していくためのナレッジ&インスピレーションの場です。もともとは雑誌としてスタートし、現在はウェブで世界中のクリエイターとつながっています。
素材の物性だけでなく、触感や光の反射、温度感までも伝えることで、アルミを“感覚的な素材”として再定義しようとしているんです。
菊池:なるほど、とても興味深いです。実は、私たちが運営しているメディア「知財図鑑」も、素材や技術の価値を多くの人に伝えるために始めたプラットフォームなんです。Hydroさんの「Shapes by Hydro」と同じように、業界や社会全体を盛り上げていきたいという思いで運営しています。こうした点で、共感できる部分は多いですね。
Jacob:そうですね。私たちは、素材の価値や可能性をデザインだけでなく、知財や技術情報を通じて共有することにも大きな意義を感じます。デザイナーや企業がHydroの素材を理解し、安心して活用できる環境を作ることは、素材の未来を広げることに直結しますから。また、ノルウェーと日本は、自然との共生意識が強いという共通点もあります。サステナビリティを軸に、ローカルなものづくりとグローバルな発信を両立させたいですね。
菊池:非常に共感します。2025年には Milan Design Week に続き、Dutch Design Week や 3daysofdesign(コペンハーゲン) にも出展されますよね。多くの企業が“社会的取り組み”を掲げながらも表面的な活動に留まる中で、Hydro社は本気で、実践的かつ意義ある取り組みを世界規模で展開していると感じます。CSRや投資家向けの姿勢ではなく、「自分たちの行動で社会を変える」という信念があるのが印象的です。

Jacob:はい。もともとはノルウェーの共同展示から始まり、現在は独自で出展しています。7名のデザイナーとコラボし、リサイクルアルミの可能性を家具やオブジェ形で表現しました。世界中の建築家、家具ブランド、メディアが訪れる中で、私たちのアプローチは大きな注目を集めました。素材を通して“美しさとサステナビリティ”を両立させることができると、多くのデザイナーが共感してくれたのです。
菊池:素材とデザインの関係性、とても興味深いですね。Milan Design Week のような国際的な舞台で素材の価値が評価されることは、デザイン業界全体にとっても大きな意味があると感じます。そこはトレンドをつくるだけの場ではなく、未来のスタンダードを形づくる場所でもある。そしてその中心に、素材メーカーであるHydro社がいるというのは非常に象徴的です。結局のところ、どれだけ素材メーカーが技術を磨いても、デザイナーをインスパイアしなければ世の中に出てくるものは変わらない。素材とデザイナーが互いに刺激し合い、共に創造することで初めて、新しい価値が社会に生まれる。その意味で、Hydro社の取り組みは単なる展示にとどまらず、未来のものづくりの在り方を提示しているように感じます。
Jacob:まさにその通りです。技術スペックだけでは人の心を動かせません。デザインは、素材が社会とつながるための「言語」なんです。Shapes by 100やデザインウィークを通じて、私たちはアルミという素材を単なる原料ではなく、社会に価値を生み出すナレッジハブとして提示しています。素材が“背景”ではなく“主役”になる瞬間をつくることが、私たちの目指すところです。

企業としての未来と、社会へのまなざし
菊池:Hydroが掲げるビジョンの中で、30年後の未来をどのように描いているのでしょうか?
Jacob:私たちが目指しているのは、“持続可能”を超えた、「viable(生き続けられる)」社会の実現です。企業は社会の中で生かされている存在であり、健全な社会なしに企業の繁栄はあり得ません。だからこそ、Hydroは「社会の持続性に貢献することで、自らの未来を築く」という信念を軸にしています。これはCSRの枠を超え、私たちの事業の根幹にある考え方です。
菊池:短期的な利益よりも、社会全体の長期的な視点を重視されていると。
Jacob:まさにその通りです。現代社会では、政治や経済がどうしても短期的な成果に流されがちです。だからこそ、企業が長期的な視野を持ち、社会の安定と再生を支える役割を担う必要があります。私たちHydroは、エネルギーと素材を通じて“社会をより良くするビジネス”を実現することを使命としています。社会が生き続けるための仕組みをつくることこそ、企業が生き残る唯一の道だと信じています。

菊池:Hydroは長い歴史の中で、さまざまな産業に携わってきましたが、今はエネルギーとアルミニウムに集中しているのですね。
Jacob:はい。過去には多くの分野に進出していましたが、現在はエネルギーとアルミニウムにフォーカスしています。これらは社会の基盤となる素材・インフラであり、私たちの強みを最大限に活かせる領域です。素材は目立たない存在かもしれません。でも、社会の“土台”を支える役割がある。だからこそ、私たちは透明性と責任をもって、次の世代にとって意味のある未来を形づくりたいのです。
菊池:素材メーカーとしての責任と覚悟が伝わってきます。素材は目立たないかもしれませんが、社会の土台を支える重要な存在であること、そしてそれを次世代に引き継ぐ使命を果たす姿勢に感銘を受けました。本日は貴重なお話をありがとうございました。
一同:ありがとうございました。
【編集後記】
「サステナブル(Sustainable)」という言葉が多くの企業で使われるなか、Hydro社はあえて「Viable Society」という表現を掲げています。それは“維持する”だけでなく、“生き続け、より良くしていく”という、より能動的な姿勢を意味します。単なる環境配慮ではなく、社会そのものを持続可能にしようとする視点。そこには、企業としての責任を超えた“生き方”としての哲学が息づいています。本気で社会をより良くしようとする企業から直接話を聞けたことは、私たちにとっても非常に貴重な経験となりました。Hydroが目指す「viable society」は、これからの時代における企業と社会の理想的な関係を示すひとつの答えなのかもしれません。
取材:菊池大樹 / 編集:勝又清





